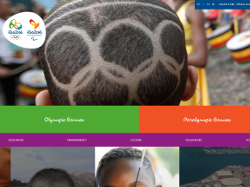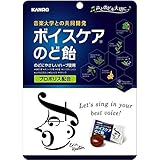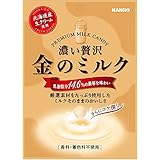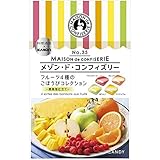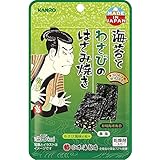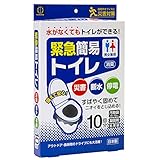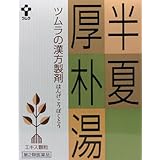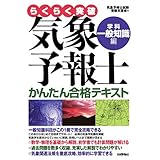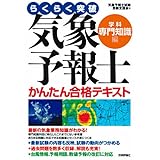● そういえば本年は閏年でしたね…
本年はどうも(3月以降)節気の度に同じ事を繰り返している様なのですが… 夕方のニュースで今日が二十四節気の一、「冬至」である事に気が付きました。
何言ってんだ?と思われるかも知れませんが…何と言うか、冬至と言えば12/22頃、と謂う頭があるので、 何かそういうきっかけでも無いと気づかないままになって仕舞うのですよ。 本年は閏年、オリンピックイヤーでしたから、 3月以降の節気は大体1日前倒しになるのでしたね。 …それにしても、その閏年ももう直ぐ終り、 月日の流れるのは速い!等と思いつつ、何やらリオ五輪ももう結構な過去の出来事と言う感じもしますねぇ。
で、その冬至のハナシです。 「冬に至る」とは雖も、今年は全国的に平年より暖かかった様ですね。 ご存知の通り、冬至と言えば(大雑把に言って)一年で最も昼の短い日。 冬の寒さはこれからが本番ですが、 日は春へ向け徐々に長くなって行きます。 この日には何時も「冬来たりなば春遠からじ」(シェリー「西風の賦」)の一節が思い浮びますね。
未だ一年最後(?)のビッグイベント・クリスマスを残して居りますが、 本年もいよいよ押し迫って参りました… もうそろそろ鬼も笑っては居られないでしょう。
■ 2017(平成29)年版カレンダー
Amazon.co.jp で人気のカレンダーから。 流石にピークは過ぎたと思われますが、 まだまだ「艦これ」人気は健在の様ですね。